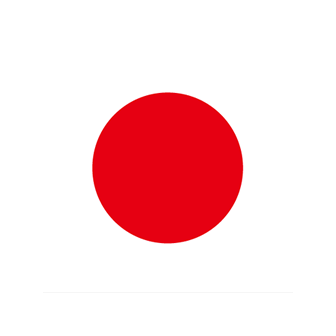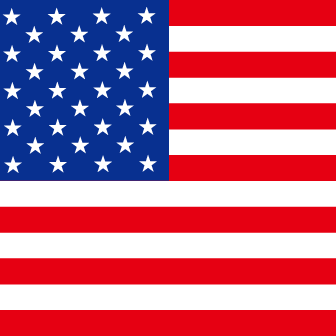日本的霊性と大地


この文章は鈴木大拙のご著書「日本的霊性(岩波新書)」からの引用です。
大地の生活は真実の生活である、信仰の生活である、偽りを入れない生活である、念仏そのものの生活である。それ故に親鸞聖人は、法然上人のもとで得たる念仏の信心を、流讁の身となった機会において大地生活の実地にこれを試さんとしたものに相違ない。京都にいる限り、この機会は決して逢着できないのである。流讁配残の身となった彼は、得たり賢しとみずからの信心に対して試練をこの機に加えたのである。彼は「念仏のみぞまことなりける」と言って、朝から晩まで空念仏のみを繰り返しはしなかったであろう。彼の念仏は実念仏であった、即ち大地に接触した念仏であった。鋤鍬を動かすもののあいだに交わってみずからもまたそれを動かしていなかったら、法然から得たという信念は、実に「そらごと、たわごと」の一種にならなければならぬのである。越後における彼の生活は、必ず実際に大地に即してものであった。彼が今までのいわゆる清浄な生活 ー 観念性にのみ富んでいて、その中にはなんらの実証的なものを含まない生活 ー に甘んじなかった事由は、その念仏を人間一般の生活の上に働き出ださんと欲したからである。然らざれば何のための「肉食妻帯」か、わけがわからないのである。彼は聖道門と浄土門との区別を、ただ「肉食妻帯」するかしないとかいうところ、専修念仏と然らざるところにのみ見んとしたのではないのである。彼は実に人間的一般の生活そのものの上に「如来の御恩」をどれほど感じ能うものかを、実際の大地の生活において試験したのである。ここに彼の信仰の真剣生を見出さなければならぬ。彼には出家とか在家とかいうものはなかった。或いはなお当時のイデオロギーを全然脱却し得なかったとしても、彼の念仏観・信心意識には、もはや旧時の「清浄な生活」などいうものはなかったのである。「煩悩熾盛」とか「地獄必定」とかいうのは、何も生活形態の外貌にのみついて言われるものではなかったのである。それ故に彼は概念生の生活をなんの躊躇もなく振り捨てたのである。彼以後の真宗教徒は、この点において猶しっかりした認識をもっていないではないかと考えられるのである。親鸞の中心思想は、如来の本願に対しての絶対信仰であって、そのほかのものに対しては ー たといそれが伝統的仏教の所説ではいかにありがたきものであっても ー それに対しては一顧をも与え得べき余裕をもっていなかったのである。
鈴木正三道人の言行を録したる『驢鞍橋』に左の文句がある。「師、任辰八月日、武州鳩谷宝勝禅寺に至る。時に近里の百姓ら数十人来り法要を問う。師示して曰く、農業すなわち仏行なり。別に用心を求めべからず。おのおのも体はこれ仏体、心はこれ仏心、業はこれ仏業也。然れども心向けの一つ悪しき故に、善根を作しながら還って地獄に入らるるなり。或いは憎い、愛い、慳い、貧いなどとさまざま私に悪心を作り出し、今生日夜苦しみ、未来は永劫悪道に堕するは、口惜しきことに非ずや。しかるあいだ農業を以て業障を尽くすべしと、大願力を起こし、一鍬一鍬に南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と耕作せば、必ず仏果に至るべし。云々。」(上巻、九八節)
これは幾千鍬を重ねることによって業障を尽くし得るという義ではないのである。南無阿弥陀仏の一鍬ごとに幾百千劫の業障が消えていくのである。鍬の数、念仏の数で業障をどうしよう、こうしようというのではないのである。振り上げる一鍬、振り下ろす一鍬が絶対である、弥陀の本願そのものに通じていくのである、否、本願そのものなのである。本願の「静かな、ささやかな声」は、鍬の一上一下に聞こえるのである。正三は禅者であるから禅語彙を用いるが、彼の無意識の意識は、深く親鸞宗の心に通うものがあるのである。親鸞の念仏は、大地から出て大地に還りゆくものであったに相違ない。彼は五年か六年かは知らないが、とにかく越後の生活でここに徹するものがあったのであろう。彼の常陸行きは、縁家の関係であったか否かを知らぬが、彼はみずからの所得底即ち無所得底を、経典の上に証してみんがため、そんな書物の入手可能な地方へ出かけたものではあるまいか。彼が青年時の煩悩が再発したものと見てよい。『教行信証』はかくして書かれた。が、また一方においては彼の言行、人格から溢れ出た弥陀信仰の光は、周囲のものを感化せずにはおれなかった。即ち教団の如きものがおのずから彼の身をめぐりて成立しかけたのは、彼が在東国の二十年間であった。在越後の数か年がなかったなら、かくの如き事象は決してあり得なかったであろう。
大地の生活は真実の生活である、信仰の生活である、偽りを入れない生活である、念仏そのものの生活である。それ故に親鸞聖人は、法然上人のもとで得たる念仏の信心を、流讁の身となった機会において大地生活の実地にこれを試さんとしたものに相違ない。京都にいる限り、この機会は決して逢着できないのである。流讁配残の身となった彼は、得たり賢しとみずからの信心に対して試練をこの機に加えたのである。彼は「念仏のみぞまことなりける」と言って、朝から晩まで空念仏のみを繰り返しはしなかったであろう。彼の念仏は実念仏であった、即ち大地に接触した念仏であった。鋤鍬を動かすもののあいだに交わってみずからもまたそれを動かしていなかったら、法然から得たという信念は、実に「そらごと、たわごと」の一種にならなければならぬのである。越後における彼の生活は、必ず実際に大地に即してものであった。彼が今までのいわゆる清浄な生活 ー 観念性にのみ富んでいて、その中にはなんらの実証的なものを含まない生活 ー に甘んじなかった事由は、その念仏を人間一般の生活の上に働き出ださんと欲したからである。然らざれば何のための「肉食妻帯」か、わけがわからないのである。彼は聖道門と浄土門との区別を、ただ「肉食妻帯」するかしないとかいうところ、専修念仏と然らざるところにのみ見んとしたのではないのである。彼は実に人間的一般の生活そのものの上に「如来の御恩」をどれほど感じ能うものかを、実際の大地の生活において試験したのである。ここに彼の信仰の真剣生を見出さなければならぬ。彼には出家とか在家とかいうものはなかった。或いはなお当時のイデオロギーを全然脱却し得なかったとしても、彼の念仏観・信心意識には、もはや旧時の「清浄な生活」などいうものはなかったのである。「煩悩熾盛」とか「地獄必定」とかいうのは、何も生活形態の外貌にのみついて言われるものではなかったのである。それ故に彼は概念生の生活をなんの躊躇もなく振り捨てたのである。彼以後の真宗教徒は、この点において猶しっかりした認識をもっていないではないかと考えられるのである。親鸞の中心思想は、如来の本願に対しての絶対信仰であって、そのほかのものに対しては ー たといそれが伝統的仏教の所説ではいかにありがたきものであっても ー それに対しては一顧をも与え得べき余裕をもっていなかったのである。
鈴木正三道人の言行を録したる『驢鞍橋』に左の文句がある。「師、任辰八月日、武州鳩谷宝勝禅寺に至る。時に近里の百姓ら数十人来り法要を問う。師示して曰く、農業すなわち仏行なり。別に用心を求めべからず。おのおのも体はこれ仏体、心はこれ仏心、業はこれ仏業也。然れども心向けの一つ悪しき故に、善根を作しながら還って地獄に入らるるなり。或いは憎い、愛い、慳い、貧いなどとさまざま私に悪心を作り出し、今生日夜苦しみ、未来は永劫悪道に堕するは、口惜しきことに非ずや。しかるあいだ農業を以て業障を尽くすべしと、大願力を起こし、一鍬一鍬に南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と耕作せば、必ず仏果に至るべし。云々。」(上巻、九八節)
これは幾千鍬を重ねることによって業障を尽くし得るという義ではないのである。南無阿弥陀仏の一鍬ごとに幾百千劫の業障が消えていくのである。鍬の数、念仏の数で業障をどうしよう、こうしようというのではないのである。振り上げる一鍬、振り下ろす一鍬が絶対である、弥陀の本願そのものに通じていくのである、否、本願そのものなのである。本願の「静かな、ささやかな声」は、鍬の一上一下に聞こえるのである。正三は禅者であるから禅語彙を用いるが、彼の無意識の意識は、深く親鸞宗の心に通うものがあるのである。親鸞の念仏は、大地から出て大地に還りゆくものであったに相違ない。彼は五年か六年かは知らないが、とにかく越後の生活でここに徹するものがあったのであろう。彼の常陸行きは、縁家の関係であったか否かを知らぬが、彼はみずからの所得底即ち無所得底を、経典の上に証してみんがため、そんな書物の入手可能な地方へ出かけたものではあるまいか。彼が青年時の煩悩が再発したものと見てよい。『教行信証』はかくして書かれた。が、また一方においては彼の言行、人格から溢れ出た弥陀信仰の光は、周囲のものを感化せずにはおれなかった。即ち教団の如きものがおのずから彼の身をめぐりて成立しかけたのは、彼が在東国の二十年間であった。在越後の数か年がなかったなら、かくの如き事象は決してあり得なかったであろう。